北海道教育大学釧路校教授 鎌田 浩子
Ⅰ 金融教育と諸教育との関連
金融教育、金融経済教育という用語を目にする機会が増えている。金融教育については様々な見解があるが、第二次世界大戦後についてみると日本銀行におかれていた貯蓄増強中央委員会による子どもへのこづかいや貯金についてのいわゆる金銭教育がわが国ではその始まりと考えられる。また、明治初期に羽仁もと子が発刊した「家庭の友」(現「婦人の友社」)による一般家庭における家計簿記帳の普及もその一端とも考えられる。
金融教育については、「お金に関わる教育のことであり、働いてお金を得ること(所得の獲得)、お金を使うこと(支出とクレジット)、お金を貯める・運用すること(金融商品)、お金を借りること(ローン・金利)などに関する教育」1)という説や「お金や金融の様々な働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて主体的に行動できる態度を養う教育」2)という説などがある。
また、金融教育と関連の大きい教育としては、経済教育や消費者教育があげられる。経済教育は、経済についての考え方を身に付け、合理的な意思決定や社会問題について考える教育である。このため、経済教育の分野は経済の基本問題(意思決定のための経済概念)、ミクロ経済、マクロ経済、国際経済に分類される3)。また、消費者教育は、消費者が商品・サービスの購入などを通して消費生活の目標・目的を達成するために必要な知識や態度を習得し、消費者の権利と役割を自覚しながら、個人としてまた社会の構成員として自己実現していく教育であり、経済教育で扱う、希少性、機会費用、トレード・オフ、意思決定プロセスなど合理的意思決定のための概念を扱うことに共通項があると考えられる4)。
これに対して、金融経済教育とは、近年金融経済教育懇親会により「国民一人一人に、金融やその背景となる経済についての基礎知識と、日々の生活の中でこうした基礎知識に立脚しつつ自立した個人として判断し意思決定能力、すなわち金融経済リテラシーを身につけてもらい、また、必要に応じその知識を充実する機会を提供すること」5)と定義が明確化されている。以上のことから金融経済教育は、これまで金融教育として貯蓄増強の視点から教育が行われていたものが、「貯蓄から投資へ」と時代の流れが変化し、投資教育、金融消費者教育など様々な側面が強調されたものと捉えることができるであろう。
Ⅱ 金融教育の現状
1 金融教育元年前後の動向
1990年代以降、わが国では日本型ビッグバンが進められ、金融市場の開放・国際化、金利の自由化、銀行・証券・保険の参入障壁の段階的廃止などの自由な金融秩序が展開しており、金融教育の必要性が高まった。海外の金融教育について見ると、米国では、既に連邦政府やFRB(連邦準備制度理事会)がNPOと連携して民主導で施策を進められてきたが、2000年に連邦政府の20省庁で構成される「金融リテラシー教育会議」が発足するなど国を挙げての新たな動きが起こっている。また、英国では、英国FSA(英国金融サービス機構)に責務として金融教育が規定されており、自主規制団体も統合する形で成立したFSAが、中央政府の教育技能省と連携し施策を推進し、さらに民間企業やNPOとも柔軟に連携して施策を形成しているのが現状である6)。
これに比べてわが国では、日本型金融ビッグバンや景気動向により金融環境が大きく変化し、金融教育の必要性が高まった。2000年金融審議会により「21世紀を支える金融の新しい仕組みについて」が答申され、その中で、金融分野における消費者教育の必要性が言及された。さらに、2002年金融広報中央委員会により「金融に関する消費者教育の推進に当たっての指針(2002)」が策定され、「金融理解度向上のための年齢層別カリキュラム(素案)」が発表された。また、2004年には、金融広報中央委員会が「全国キャラバン金融講座」を全国21ヶ所で開催、また、金融庁が主催し「金融経済教育シンポジウム」を初めて開催、金融庁が「金融改革プログラム」を策定・公表するなど著しい動きがあった。さらに、2005年には、金融庁が「金融経済教育懇談会」を設置し、活動を拡充、金融広報中央委員会は「金融教育ガイドブック―学校における実践事例集―」を作成し、さらにこの年を「金融教育元年」と位置づけた。そして、2008年金融広報中央委員会は「金融教育プログラム―社会の中で生きる力を育む授業とは―」を発行した。
2 金融教育プログラムにおける金融教育の目標と4つの分野
2008年に発刊された「金融教育プログラム―社会の中で生きる力を育む教育とは―」は、学校教育における金融教育をより効果的にすすめるために、小学校・中学校・高等学校の学校段階ごとに各教科や総合的な学習の時間等における金融教育の指導計画事例等を中心に編集されたものである。
そして、ここでは現実の社会の中で生きていくのに必要な金融・経済などの知識やお金を適切に取り扱う態度を身につけることなどを目的として、金融教育を「経済や金融の仕組みに関する分野」「生活設計・家計管理に関する分野」「消費生活・金融トラブル防止に関する分野」「キャリア教育に関する分野」の4つの分野としている。7)そして「生き方や価値観の形成」を目的として「よりよい生活と社会づくりへの取り組み」のために「お金」をめぐる「お金のはたらき」をはじめとする13のコマを連動して学習することが示されている。(図1)このように、現在の金融教育プログラムは、学校教育を中心として、金融経済教育のみならず、生活設計・家計管理や消費生活・金融トラブル防止等消費者教育と大きく関連をもちながら実践がすすめられている。また、2004年の消費者基本法により消費者に権利の一つとして「消費者教育を受ける権利」があげられている。以上のことから、特に家庭科教育における金融教育は、「生活設計・家計管理に関する分野」「消費生活・金融トラブル防止に関する分野」「キャリア教育に関する分野」の3つの分野と大きく関わって行われている。
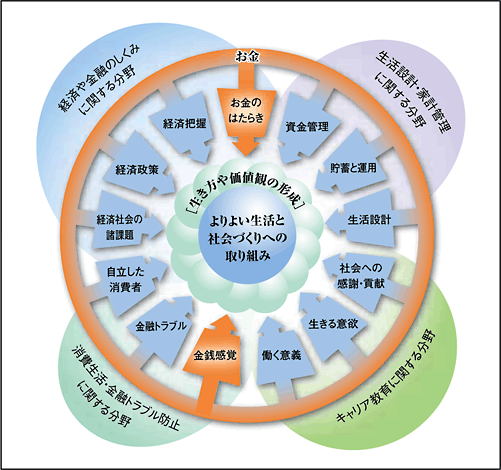
出典:図1 金融教育の目標と4つの分野
(出典「金融教育プログラム」金融広報中央委員会(2007))
Ⅲ 新学習指導要領における金融教育
1 新学習指導要領の特徴と金融教育
新しい学習指導要領が告示され、平成21年度からの幼稚園を筆頭に平成23年度からは小学校、平成24年度は中学校で順次全面実施となる。(表)ここでは、小・中・高等学校の学習指導要領についてみることにする。
今回の学習指導要領の改訂の基本的な考え方は、以下の3つである。
(1) 教育基本法改正で明確になった教育の理念を踏まえ、「生きる力」を育成
(2) 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視、授業時間を増加
(3) 道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成
授業時間数についてみると、小学校では、国語、社会、算数、理科、体育を10%増加、週あたりのコマ数を低学年で週2コマ、中・高等学年で週1コマ増加した。中学校では、国語、社会、数学、理科、外国語、保健体育の授業を実質10%程度増加し、週当たりのコマ数を1コマ増加する。高等学校については、卒業までに修得させる単位数は、現行通り74単位以上だが、共通性と多様性のバランスを重視し、学習の基盤となる国語、数学、外国語に共通必履修科目を設定するとともに、理科の科目履修の柔軟性を向上させた。さらに週当たりの授業時数(全日制)は標準である30単位時間を超えて授業ができることを明瞭化したことなどがあげられる。
教育内容の主な改善点として、言語活動の充実、理数教育の充実、伝統や文化に関する教育の充実、道徳の充実、体験活動の充実、外国語教育の充実、高等学校ではさらに職業に関する教科・科目の改善などがあげられている。
そして、金融教育は、「生きる力」を育むことを目指した教育であると考えられる。
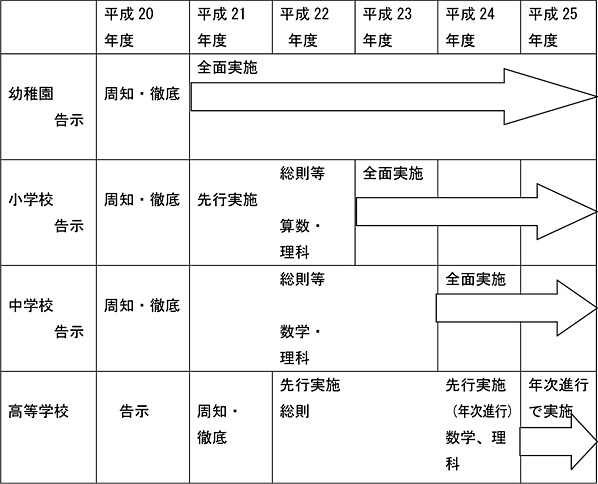
2 新学習指導要領における記述例
以下は、新学習指導要領の金融教育の内容の記述例である。消費者教育の内容も含め広く抽出した。
(1) 小学校<平成20年3月告示>| 社会科 ・食料生産・工業生産に関わって、価格や費用を取り扱う(第5学年) ・租税の役割、納税義務などについても取り扱う(第6学年) |
| 家庭科 ・物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考える(第5・6学年) ・身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できること(第5・6学年) |
| 道徳 ・物や金銭を大切にする(第1・2学年)(同旨第3・4学年、第5.6学年) |
(2) 中学校<平成20年3月告示>
| 社会科(公民的分野) ・身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させる ・価格の働きに着目させて市場経済の基本的な考え方を理解させる ・現代社会の生産や金融などの仕組みや働きを理解させる |
| 技術・家庭科(家庭分野) ・自分や家族の消費生活に関心を持ち、消費者の基本的な権利と責任について理解すること ・販売方法の特徴について知り、生活に必要な物資・サービスの適切な選択・購入及び活用ができること |
(3) 高等学校<平成21年3月告示>
| 公民科(現代社会、政治・経済) ・経済活動の意義について理解させる ・市場経済の機能と限界に関して、公害防止と環境保全、消費者問題も扱う ・金融の仕組みと働きに関して、金融に関する環境の変化にも触れる |
| 家庭科(家庭基礎、家庭総合、生活デザイン) ・消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任を理解させる ・消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させ、消費者として主体的に行動できるよう にする ・生涯を見通した経済の管理や計画の重要性について認識させる ・契約・消費者信用及びそれらをめぐる問題などを取り上げて具体的に扱う(多重債務問題含む) ・ 消費生活の現状と課題、消費者問題や消費者の自立と支援などについて理解させる |
Ⅳ 家庭科における金融教育
金融教育は、社会科、道徳等の授業で実施されているが、高等学校では、社会科公民は選択科目であるため、生徒が必ず学習するのは家庭科である。そこでここでは家庭科に注目して考察を行う。
サブプライムローン問題の発生に端を発した世界的経済危機により、わが国でも消費者の経済的自立について学校教育で教えることが必要であることが認識されたといえる。特に、高等学校の新学習指導要領では、「消費生活と生涯を見通した生活における経済の管理や計画」(家庭基礎)、「生活における経済の計画」(家庭総合)等「経済の計画」の項目が立てられ、さらに指導要領解説には「リスク管理」の内容も新しく設けられた。これまでの家庭科の学習指導要領改訂で、高等学校で家計簿記帳や、小学校でこづかいの記帳の項目が削除されてきた経過に比べ、今回の改訂では逆に「経済の管理や計画」が重視されたといえる。
これまで家庭科における金融教育は、「国民経済と家庭生活」として、家計の構造や経済システム全体についての学習や「消費生活や消費者の主体的な判断」として「クーリング・オフ」「自己破産」などを中心とした学習が中心であった。しかし今後は「生涯を見通した経済の管理や計画」がキーワードとなるだろう。今後の金融教育は、子どもにとって身近なこと、例えば金融サービスについて、ネット決済や携帯電話やチャージ式カードなど多様なサービスについての知識を始めとして、生活設計に貯蓄や保険、クレジットカードなどについてリスク管理を含めて広く学習していくことが必要であり、これらをどのようにそれぞれの子どもの生活と近づけて教えていくことができるかが今後の課題である。
| 1) | 日本消費者教育学会編「新消費者教育Q&A」中部日本教育文化社 pp14-15(2007) |
| 2) | 金融広報中央委員会「金融教育プログラム」P10(2007) |
| 3) | 前掲1)P44 |
| 4) | 前掲1)P7 |
| 5) | 金融経済教育懇談会「金融経済教育に関する論点整理」P1(2005) |
| 6) | 金融広報中央委員会「グローバルに拡大する金融教育のニーズと英国における金融教育の動向」pp.13~18 |
2.学校における金融教育の実際
標茶町立虹別小学校教諭 野口 泰秀
| [1] | 小学校の金融教育とは? | ||
| (ア) | 初等教育における金融教育の必要性 小学生に金融教育は必要であろうか? 私が、金融教育のプロジェクト会議に参加したときは、小学生にお金の勉強なんて…。とか、少々、難しいのでは…等、半信半疑であった。しかし、小学生であっても、お小遣いをもらったり、お金を使って買い物をすることが当たり前の世の中であり、すでにお金とのお付き合いは始まっている。また、様々なリスクとリターンの可能性を含んだ多様な金融商品の開発、多重債務による自己破産者の増加、振り込め詐欺などといった社会問題がメディアによって目の当たりにするとともに、将来において、更なる高齢化社会の到来や雇用形態の変化による多様な生活設計・資金管理の選択と必要性等が生まれている。 このような、金融をめぐる社会状況の急激な変化の中で、小学生でも、お金や金融の様々な働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考えることが求められている。このことから、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて主体的に行動できる人間を育てるために、学校教育における適切な金融教育の導入が必要である。 |
||
| (イ) | 小学校の金融教育 それでは、小学校において金融教育をどのように進めていくとよいのだろうか?まず、児童生徒の発達特性に応じた指導内容の配慮が必要となる。金融教育の指導内容には、内的側面と外的側面が存在する。内的側面とは、ものの大切さ、約束の遵守、欲望の制御、リスクの管理、意思決定、自己責任、将来への希望等である。また、外的側面とは、貯蓄、交換や市場の機能、各種カードの機能、消費者トラブルの実情、借入の仕組み、各種金融商品の知識等であり、お互いが有機的に結びついている。  小学校の段階では、特に、内的側面を重視した学習展開が大切であり、中学校や高等学校等学年が上がることによって、徐々に外的側面を重視した学習展開へと移行していく。 小学校の段階では、特に、内的側面を重視した学習展開が大切であり、中学校や高等学校等学年が上がることによって、徐々に外的側面を重視した学習展開へと移行していく。そこで、金融広報中央委員会が発刊している金融教育プログラムに記載されている年齢層別の金融教育内容を参考にしながら小学校段階の目標と内容、主な単元構想・題材・資料についてまとめ、児童の発達段階と各学年の教科・領域の目標を照らしながら、表1のように学習活動を具体的に洗い出した。 |
||
|
|||
| 表1 小学校における金融教育の目標と内容、主な学習活動 |
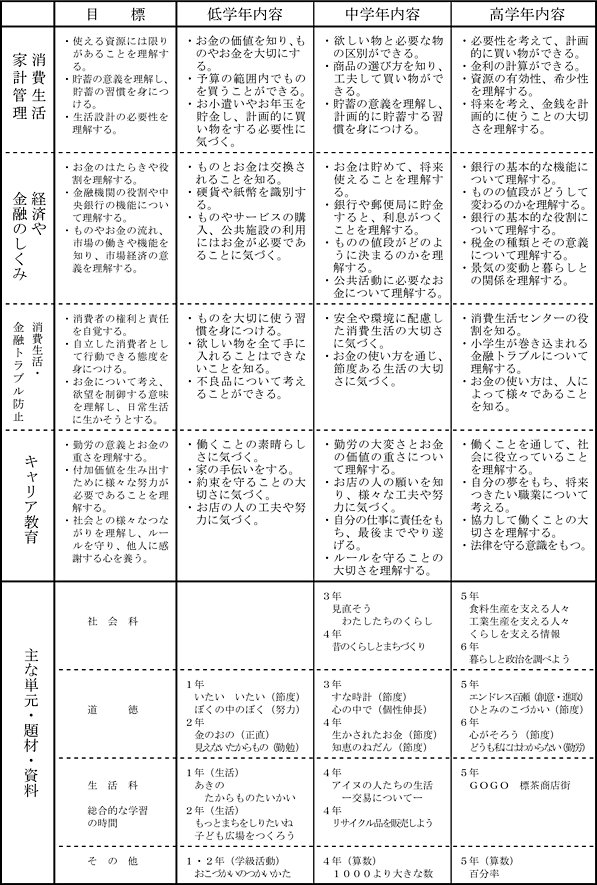 |
| [2] | 金融教育の授業ってどうやればいいの? | ||
| (ア) | ものを大切にする気持ち・約束を守る気持ちを育てることからはじめよう 金融教育と言うと、お金、貨幣、貯蓄、消費・・という言葉がイメージできる。しかし、内的側面を大切にする小学校の金融教育は、まず、ものを大切にする気持ちや約束を守る気持ちを育てることから始める必要がある。 なぜならば、お金を扱う場合、そこには大きな信頼関係が必要不可欠だからである。信頼関係は、自他のものを大切にする態度や約束をしっかり守ることが基盤となるからである。そして、このことは、学校生活全ての教育活動で育てていくことが大切なのである。 ちょっと教室の中をのぞいてみてはいかがであろうか?ゴミが普通に落ちていることはないだろうか?机が曲がっていても平気ではないだろうか?誰かの鉛筆が落ちていたら、「だれのですか?」と聞いてあげられる子どもたちだろうか?授業前に教科書などは正しく準備されているだろうか?……等、小さなことではあるが、小さな事を大切に指導することが真の意味での金融教育を実施できる素地がつくられるはずである。 |
||
| (イ) | 金融教育はどの教科や領域で学習するのだろうか? 新学習指導要領では、新たに5年生社会科において、「食料生産及び工業生産の価格や費用」について取り上げることとなった。これは、金融や経済に関する基礎的な知識を身につけさせることがねらいである。また、家庭科においては、現行学習指導要領から引き続き、「物や金銭の使い方と買い物」について取り上げるようになっている。勿論、生活科や道徳、特別活動、総合的な学習の時間においても、金融にかかわる内容を取り上げることは可能である。 さらに、中学校や高等学校との違いで考えるならば、小学校は、担任がほぼ全ての教科を担任するため、1つの教科に縛られることなく、教科・領域の関連を考えた『学びが広がる単元活動』の構想をもつことができるのである。たとえば、生活科を核としながら、図工科や算数科との関連を考えた単元(例1)や社会科と算数科をクロスさせたカリキュラムによる単元を構想し、広い視野から金融について触れていく機会の設定が可能となる。 |
||
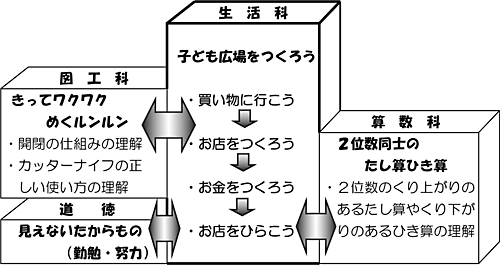
| [3] | 金融教育の授業の実際 | ||
| (ア) | 金融教育 小学校低学年生活科 |
||
児 童:2学年 男子6名 女子3名 計9名
| 1 | .単元名 子ども広場をつくろう(第2学年 生活科他) | |||||||
| 2 | .単元について | |||||||
| (1) | 金融教育と生活科とのかかわり 現行学習指導要領には八つの内容が示され、その一つに「生活と消費」に関する視点がある。そこでは、生活に必要なものを買ったり、計画的に使ったりすることができるように示されている。例えば、自分たちの生活と地域のお店の人たちとのかかわりを通して買い物に対する関心を高めたり(内容(3))、地域の公共物や公共施設を利用するときに、お金が必要であることに気づいたりする(内容(4))ことである。新学習指導要領においても「生活と消費」に関する視点は以下の通り示されており、今回、提案する授業実践は、新学習指導要領にも対応している。
|
|||||||
| (2) | 学びが広がる単元活動の構想について 単元活動「子ども広場をつくろう」は、道具や材料など身近にあるものを大切にし、友達と仲良く利用したり、目的に応じて使用したりしながら、買い物体験を生かした表現活動を行い、自らの生活を工夫することが大きなねらいとなる。特に、身近にあるものを大切にすることや目的に応じて使用することは、自立する力の育成支援と社会とかかわる力の育成支援を唱える金融教育の意義と相互にかかわる。 また、金融広報中央委員会が発刊した「金融教育プログラム」によると4分野13項目による内容一覧が提示されている。本単元活動においては、全てを網羅するものではないが、内容一覧をもとに、次のように4分野7項目から子どもに身につけたい力を明確にした。
|
|||||||
| また、単元活動「子ども広場をつくろう」は、子どもに身に付けたい力の実現を目指し、次のように生活科を核としながら、図工科及び算数科の時間を活用しながら4つのユニットで構想した。これは、2年生である本学級の子どもの実態を考慮したものである。低学年の場合、大単元をいくつかのユニットに分け、短いサイクルで学習に取り組む方が、集中力が持続し、効率的に進めていくことができると判断したからである。 このような考えのもと、子ども一人一人に金融教育の内的側面を高めるともに、実際に教室マネーを使った取り組みを行うことで、お金の価値やものとお金が交換できることを実感させたい。 |
||||||||
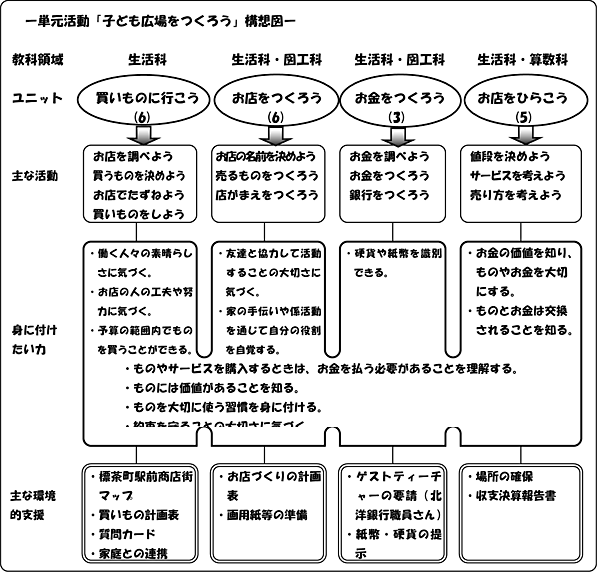
| 3 | .単元目標 単元活動の目標 |
|
| ○ | 買い物体験を通して、身近な商店で働く人たちの工夫や努力に気づくとともに、決められた予算の範囲で必要なものを購入することができるようにする。 | |
| ○ | お店作りやお店開きを通して、身近にあるものの価値観を知り、大切に使うことができるとともに、友達と仲良く活動し、約束を守る大切さに気づくようにする。 | |
| ○ | 硬貨や紙幣の識別ができ、ものやサービスを購入するときには、お金を払う必要があることを理解しようとする。 |
|
| 4 | .単元ユニットの指導計画(お金をつくろう…3時間扱い) | |
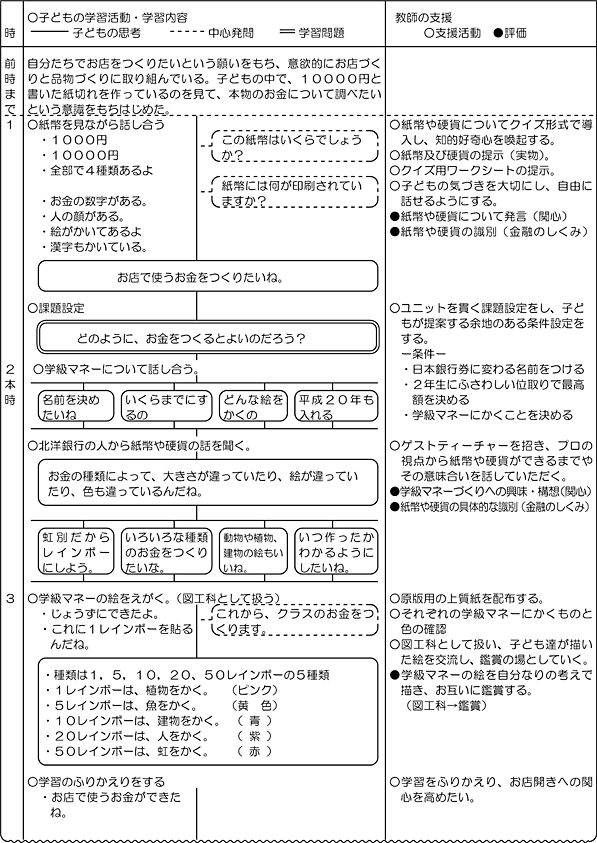
| 5 | .本時の目標(2/3時間) 友達との話し合いや銀行の方の話を聞き、紙幣や硬貨の識別について理解を深めるとともに、自分たちの学級にふさわしい学級マネーについて具体的な構想をもつことができる。 |
| 6 | .本時の学習の視点 単元ユニット『お金をつくろう』は、自分たちのお店で使ってもらう学級マネーをつくることが大きなねらいであり、そのために、紙幣や硬貨の識別を行うことになる。 本時においては、低学年ということを考慮し、学級マネーについて、一定の条件設定の中で子ども達が自由に提案できるようにしている。また、ゲストティーチャーを招き、プロの視点から紙幣や硬貨についての話をしていただくことによって、子ども達の提案にシャープさが増し、思いつきではなく紙幣や硬貨がつくられた意味合いが含まれることをねらっている。 |
| 7 | .本時の展開 |
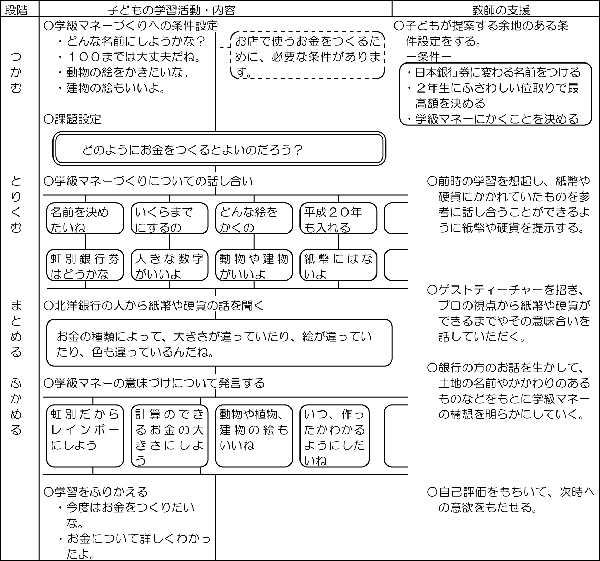
| 8 |  .本時の評価 .本時の評価友達との話し合いや銀行の方の話を聞き、紙幣や硬貨の識別について理解を深めるとともに、自分たちの学級にふさわしい学級マネーについて具体的な構想をもつことができたか。 |
| [3] | 金融教育の授業の実際 | ||
| (イ) | 金融教育 小学校中学年総合的な学習の時間プラン |
||
| 1 | .単元名 リサイクル品を販売しよう(第4学年 社会科、総合的な学習の時間他) |
|
| 2 | .単元活動について 米国では、環境教育を推進するために、子ども達が作ったリサイクル品を販売しているところがある。本単元においては、総合的な学習の時間を核としながら、社会科及び国語科、そして、道徳を関連させた単元活動である。日常のごみの捨て方をとらえ返し、環境を壊さないようにする意識を育て、同時にリサイクル品の開発と制作、そして販売の体験を行う学習として位置付けた。特に、金融教育の視点で単元を見たときに、次のような力を身に付ける可能性がある。
これらの考えのもと、授業プランを単元レベルで作成してみた。まだ、実践はしていないが、リサイクル品に対する価値観や付加価値を学ぶ学習になると思う。 |
|
| 3 | .単元目標 単元活動の目標 ○友達と協力しながらリサイクル商品の開発と販売を進めようとする。 ○資源の有限性や希少性などに課題意識をもち、リサイクル品を開発しようとする。 ○自分の役割に責任をもち、繰り返し取り組もうとする。 |
|
| 4 | .単元活動の構想 |
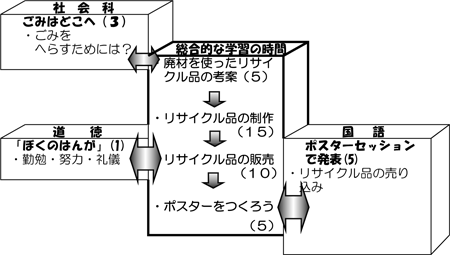
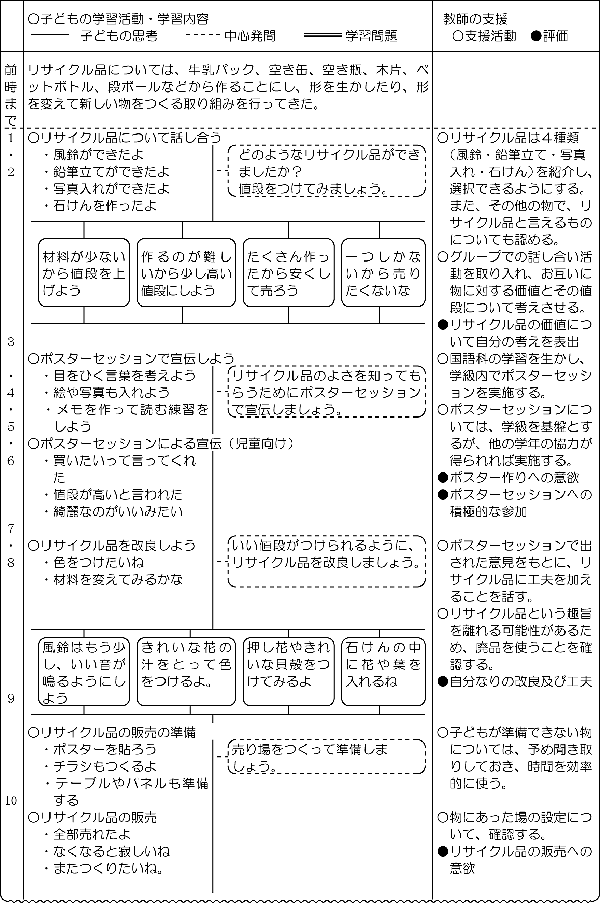
・ 2年生 生活科 かいものたんけんカード PDF
・ 2年生 生活科 お店をつくろう PDF
・ 1年生 せいかつ おかいものをしよう PDF
・ 2年生 生活科 いくらになったかな? PDF
・ 2年生 生活科 お金をしらべよう? PDF
(2)中学校における金融教育の実際
はじめに
中学校は教科担任制による教科専門の学習指導をすすめている。その中で「金融教育」には社会科の教科性が強く感じられる。確かに、具体的な金融のしくみに始まり、家計や国家財政、さらには国際金融に至るまで広い金融の対象が中学校社会科・高等学校公民科の学習内容として位置づけられている。学校での金融教育の必要性が、現代社会の変化に対応し、社会的に自立した人間としての基礎を培うことの重要性にあるように、学校で学んで終わりという金融教育であってはならない。学ぶ知識と現実の生活が結び付き、子どもたちにとって、これから出会うさまざまな社会での場面に適切に対応していく力をどのように身に付けさせていくのかが金融教育のみならず、広く現代教育の課題である。ここでは、中学校社会科での金融教育の考え方と実践について述べ、今後取り組むべきことを考えていきたい。
| [1] | 中学校社会科での金融教育の位置付け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | )公民的分野-経済単元での「金融教育」 中学校社会科では、「金融」という言葉は公民的分野の経済単元でのイメージが強い。確かに、公民的分野の経済単元では、家計から国家財政までの広い経済活動を教材とする中で、金融のしくみの基本的なことについての学習をする。 現在、札幌市で採択されている公民的分野の教科書では、以下のような内容構成の中で、金融の役割、金融機関のはたらきなどを学習している。
実際の授業の中でも、教科書で解説されている言葉の多くは、生徒の生活経験の中ですでに出会ってきているものも多く、生徒自身に興味をもって学習に臨ませることが比較的しやすい部分でもある。しかし、公民的分野で現代社会の金融について学ぶこと以前に、地理的分野と歴史的分野での学習でも、金融にかかわることを学んでいる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | )地理的分野・歴史的分野での「金融教育」 現在、札幌市で採択されている地理的分野と歴史的分野の教科書の内容について、金融にかかわる部分を大まかに見てみると、以下のようなことが整理できる。
特に歴史的分野では、縄文時代の物々交換に始まり、奈良時代の富本銭や室町時代の日明貿易での輸入貨幣、江戸時代末期の開国による金の流出と物価の関係、明治初期の地租改正と銀行開設など、学習内容に金融にかかわることが多くみられる。現代社会とは同じでなくとも、その時代の歴史的事象の特色をつかむためには、金融のしくみの基礎的な理解は必要となるのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | )中学校社会科の各領域の金融に関する系統性 地理・歴史・公民の3つの分野の学習内容に、それぞれの分野の学習の特色に応じた金融にかかわる理解が必要となる。もちろん、技術・家庭科との内容的な関連性、道徳の内容項目などとも結び付けていくことが必要であり、中学校の教育課程の中での系統性も考慮しなくてはならないが、ここでは社会科の分野間に限定している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<中学校社会科の各領域の金融に関する系統性と内容例>
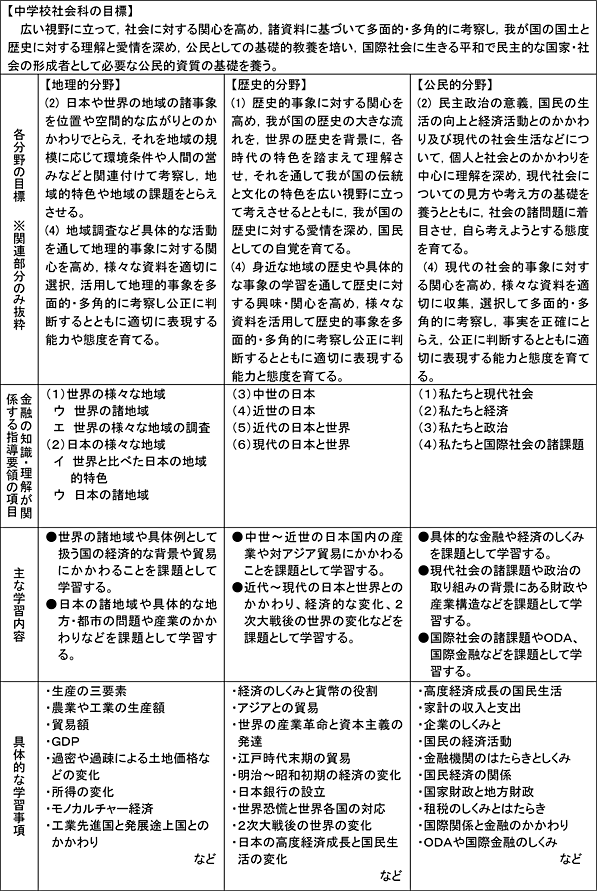
| [2] | 授業の実践 | ||
| a | )歴史的分野での実践~「日清・日露戦争期の日本の経済の変化」~ | ||
| ア | .本時のねらい 日清・日露戦争前後の「日本の産業革命期」の国内の経済や産業について、さまざまな産業の成長と金融制度の整備の2つの視点から見つめ、日本の産業の近代化のしくみや課題を理解する。 |
||
| イ | .本時の展開 | ||
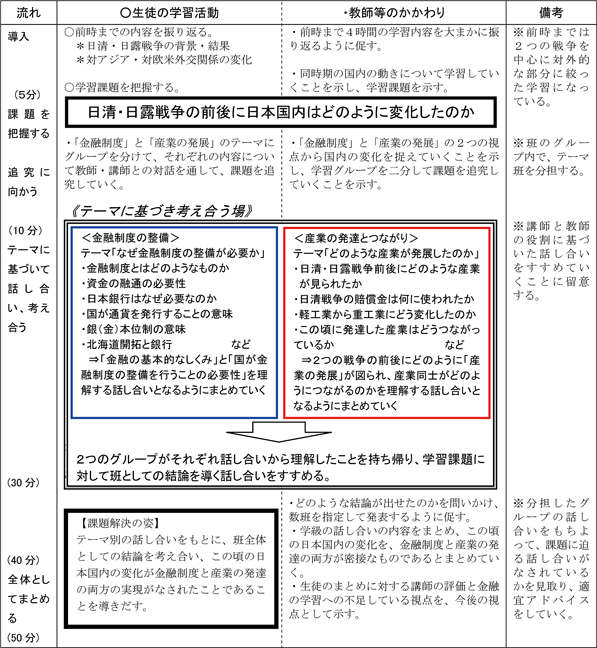
| a | ウ | .本時の評価 日清・日露戦争前後の「日本の産業革命期」の国内の経済や産業について、さまざまな産業の成長と金融制度の整備の2つのテーマで考え、国内の産業の変化とこの時期に金融制度を整備することの必要性を結びつけて理解することができたかを、グループの交流やワークシートの記述から見取る。 |
|
| エ | .本実践を振り返って 本実践は、歴史的分野での金融教育を意識して行ったものである。明治後期の「日本の産業革命」と呼ばれる時期の学習として、工業化の進展と日本銀行などの金融制度の確立を関連させて教材化を進めた。この当時の日本の工業分野や産業を人間の体の各器官に例え、金融を血液に例えた。各器官が動くためには、血液が必要であり、各器官は互いに関連しあっている。各器官が成長したり活発になったりすれば、それを動かす血液もまた多く必要になる。血液の流れが悪くなれば器官のはたらきも弱まり、その逆も起こってしまうというイメージをもとに、授業づくりを進めた。 金融制度のしくみや必要性については、北洋銀行の方にゲストティーチャーとして入っていただき、具体的な説明をしていただいた。金融のしくみを歴史的分野に取り入れることで、近現代の社会変化と共に金融のしくみが変化していくことを、歴史的な見方に組み入れ、公民的分野につなげることを意図した。ゲストティーチャーとは、何度も授業の打合せが必要であり、そのために授業構成を綿密に行わなくてはならない。 生徒は、金融のしくみと歴史的な事実を結びつけて、「だから金融のしくみを整備することが必要なんだ」ということと、「金融のしくみがなければ、この時期の経済成長は困難だったんだ」ということに気付いていった。 |
||
| b | )公民的分野(経済単元)での実践~景気変動による経済活動の関連~ | ||
| ア |  .関連づけから、金融のしくみを考える .関連づけから、金融のしくみを考えるこの実践では、景気が変動することにより物価や税収、借り入れや公共事業の増減などがどのように変化していくかを、考えさせることをねらいとしたものである。 好景気の時の基本形を、【生産<消費】として、物価・所得・株価・失業者数・倒産・税収・国債・利子・借り入れ・公共投資の各項目が増加と減少のどちらにシフトしていくかを考えさせ、座標上に示させた。 右の図のように、好景気を基準に考えさせ、好景気が持続した時のメリットとデメリットを経済の動き全体のこととして総括し、意見交流をする中でポイントを焦点化した。また、不景気の時は、各項目の動きが原則として正反対に位置付いていくことを示し、好景気と不景気の立場の対称性を理解させた。生徒の思考の結論としては、好景気と不景気のそれぞれに応じた景気対策が必要になることに気付いていった。 |
||
| イ | .「借り入れ」の項目の意見の相違 好景気の時には、借り入れ(政府以外の借金)は増えるのか減るのか。この項目に対して意見が分かれることで、金融のしくみに着目させることもこの授業のねらいの一つであった。この項目は、何を主語において考えるかで導かれる結論が異なる。 「景気がいいのだから、収入が増えれば、特に借金は必要ないから借金は増えないはず」「売り上げが増えるのだから、もっと工場を作ったりして生産を増やせばいい。そのためには資金としての借金は増えるはず」という意見が出された。現実にはどちらも正解である。政府の税収と国債の関係や、好景気の時の利子率の上昇をもとに、二通りの意見が出され、その理由を考えることを通して、金融のしくみの理解を深めることをすすめた。 |
||
| ウ | .本実践を振り返って 公民的分野の経済単元は、家計・企業・政府の三者による経済活動を結び付けて、経済を動態的を捉えさせることをめざした。その中で、金融のしくみについても、立場の違いに着目させることで二つの動きが出てくることを理解させることができた。 経済単元では、金融機関のしくみを学習することと、経済全体のかかわりの中で金融のはたらきを考えさせることの両方が必要であることを、本実践から確認することができた。半面で、好景気・不景気の時に金融機関としては、どのように経済全体の動きにはたらきかけるのかはわからない。本実践にもゲストティーチャーを招き、生徒の思考だけでは解決できない課題に取り組ませることも、金融の理解を深めるためには有効なことになりうると考える。 |
||
| [3] | 社会科としての課題 | ||
| 冒頭に述べたように、「金融教育」には社会科の教科性が強く感じられる。しかも、経済に関する学習の一部として、内容を捉えるのが一般的であろう。しかし、中学校社会科の各分野の関連付けを図り、金融教育のねらいとその分野や内容に応じた学習を構成していくことが大切だと考える。金融に関する知識は、「知らないと困る」という危険性の側面ではなく、自分がより豊かに生活するためにという側面から進めるべきだと考える。 高等学校の公民科(政治・経済)は、必ずしも高校生全員が学習するものではない。それだけに、中学校の社会科での金融教育は、社会人としての基礎力を養っているという立場ですすめていかなくてはならない。今後は、金融教育のねらいとその分野や内容に応じた学習をさらに具体化し、実践を進めていくことで「中学校社会科の金融教育」のモデルを形成していくことが必要であろう。銀行の方を授業に招聘して、金融のしくみを説明してもらったり、投融資ゲームを行ったりすることが、金融教育として一般的な実践となっている。生徒にとっては、一回限りの学習の終わっては、実際の生活につながるものにはならない。身近な生活や国際関係に至るまで、学習のねらいに即して金融のしくみを理解していく場面が必要となる。小学校・各教科等との関連を図ること、実際の金融機関とかかわること、生活経験を結び付いていることを重視して「中学校社会科の金融教育」を考えることが、これからの金融教育を推進していく上での課題であると考える。 |
|||
(2)中学校における金融教育の実際
本プロジェクト『金融教育』を実践するにあたり,当時,本校の教育課程にあった「選択教科家庭科」または「総合的な学習の時間」を充当して実践することを考えた。「金融」という語句が学習指導要領の家庭分野ではふれられていないこと,必修家庭科では授業時数に盛り込むことが難しいからである。
そこで題材名『金融教育』の授業の展開においては,[1]"お金の管理"という言葉を理解させるため,具体例を「短期間,または中・長期間の金銭の取扱い方」「人の意思で金銭が利用される場面」に絞ること [2]中学生の興味・関心を喚起させるため,時事的な話題・事件を積極的に取り入れること等の工夫を考え実践することとした。
2 金融教育と教科(分野)との関係
|
||||||||||
本校家庭科では,「D身近な消費生活と環境」として,題材名「わたしたちの消費生活と環境」を3学年で設定している。授業では,「中学生や家族にかかわる消費者問題の事例の原因を探る活動を通して,契約の意味と重要性を理解させる」「クーリングオフ制度のしくみを理解させ,消費者問題に遭遇しても積極的に解決を図ろうとする態度を育てる」等を学習目標として授業の工夫を行っている。「わたしたちの消費生活と環境」8時間に続いては,題材名「環境や資源を考えた生活(=エコクッキングの取組を通して,環境や資源に配慮した生活の実現へ向けて意識を高めさせる授業)」10時間を実践し,3年間の家庭分野の学習を終える。
本校における「金融教育」を実践するにあたっては,"金融=貨幣の信用取引"であることから,生徒が自己の将来を見通して「消費者金融のしくみ」「個人財産の管理の必要性」について理解できるよう授業計画を作成し,卒業間近の1~2月に授業を行った。
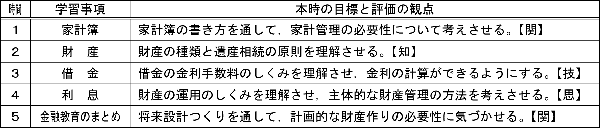
(2)中学校における金融教育の実際
そこで、学習指導要領に照らし合わせながら、学習の中で「賢い消費者」として生徒に押さえさせたいことを、次のようにまとめてみた。
| [1] 消費者の「権利」と「義務」として、「契約」の意味と重みを知ること [2] 本当に必要なものを、確かな情報で選択し、確かな場所で、安心のある購入をすること [3] 自分の収入と支出に見合った購入計画をたてられること [4] 悪徳商法の被害にあわない知識と対処方法を身に付けること [5] 消費者を守る制度や法律を知ること [6] 消費者として環境に配慮した生活ができること |
さて、上記の[1]~[6]のことを限られた時間の中で教えるためには、具体的な工夫が必要である。
(1) 小学校家庭科との接続を意識する(小学校の学習を踏まえて考える)
小学校における『D 身近な消費生活と環境』の指導について、小学校学習指導要領解説家庭科編では、「A(3)「家族や近隣の人々とのかかわり」や「B日常の食事と調理の基礎」または「C快適な衣服と住まい」の内容と関連を図ることにより、衣食住などの生活で使う身近なものなどを取り上げ、児童や家族の生活と結びつけて考え、実践的に学習できるようにする」と記されている。実際の授業では、児童の発達段階で考えれば抽象的な概念は扱いづらいので、例えば調理実習に必要になるものを買いに出かけるなどの「体験的な学習」を取り入れ、具体的な操作の中で生活の場面と結びつけて知識や考え方を身に付けさせる場合が多いと考える。どのような題材で、どのような体験的な学習をしてきたかは、地域や学校、児童の実態に応じて違うであろうから、小学校でどのような内容を取り扱っているか学習をしてきたかを事前に把握しておくことが大切である。方法としては、生徒に対するアンケート調査や地域の小学校、中学校の教師間で具体的な題材や学習内容の取り扱いについて交流しておくことが考えられる。
これにより、学習内容の無駄な重複を避けることでできると同時に、小・中相互に基礎・基本の厳選も可能になると考える。※資料参照
(2) 体験的な活動を重視した題材(教材)開発
中学校家庭科においても小学校同様、「体験的な活動を重視する」という基本的なスタンスは同じである。しかし、時数や学習内容を考えた場合、全てを「体験的な活動」でというわけにはなかなかいかないのが実際のところである。だからといって抽象的な話ばかりの一方通行的な学習になると実際の生活場面と乖離してしまって、生徒の学習に対する興味・関心も薄れていくので注意が必要である。
したがって、授業では「○○のような場合、あなたはどうしますか?」というような生徒の価値観を揺さぶるような課題を設定し、シュミレーションやロールプレイなどの疑似体験を通しながら学習のねらいに迫るのが効果的であると考える。
課題を設定する際には、次のことに注意するとよい。(1)で述べたように、教科として押さえるべき基礎・基本が厳選できれば、生徒の活動を保証する余剰時間を生み出すことができると考える。教えるところはしっかり教える、考えさせて深めさせたいところは時間をかけるなどのメリハリが必要である。
| ○生徒の生活経験や消費生活に対する実態などを調査し、課題の有用性や難易度などを検討すること。 ○話し合いや討議の場を取り入れることで、生徒個々の思考力、判断力が高まるようにすること。 |
社会や数学などの各教科、特活、道徳、総合的な学習との横断的なつながりも意識することも大切である。金融教育という一本の柱を立て、教育課程全体でできることを明らかにできれば、生徒が学習の中で得た自分の知識や考え方をネットワーク化ができるので一層の学習効果が期待できます。また、そのような「考え方」や「学び方」を身に付けること自体も『生きる力』を培ううえでも大切である。
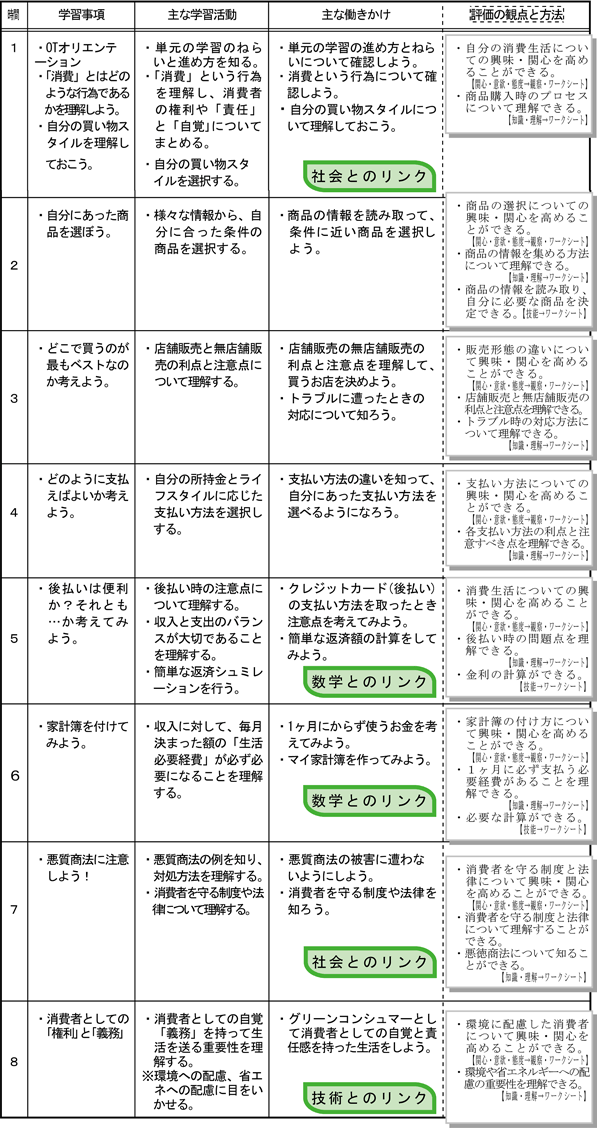
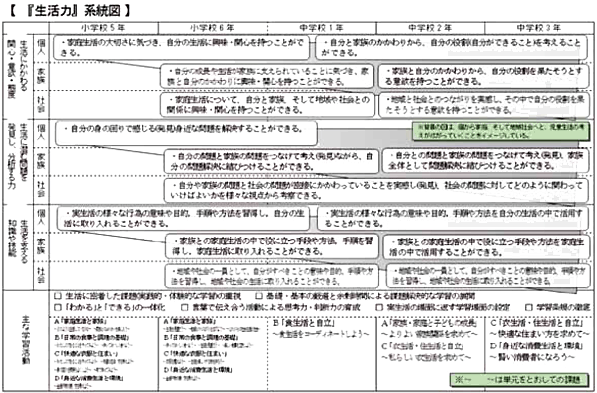
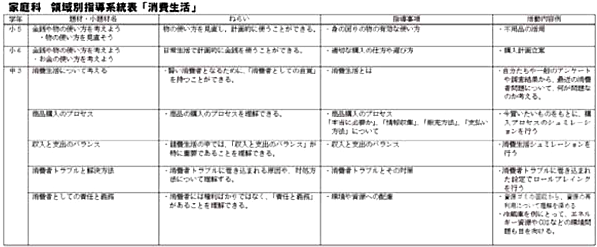
【参考文献】
・「小学校学習指導要領解説家庭科編」文部科学省東洋館出版社2008/8/31
・「中学校学習指導要領解説技術・家庭科編」文部科学省教育図書2008/9/25
・「新しい技術・家庭家庭分野指導資料編」東京書籍
・「北海道教育大学附属釧路小中学校研究紀要」2005~2008
・ 政府公報オンラインhttp://www.gov-online.go.jp/useful/article/200805/2.html
(3)高等学校における金融教育の実際
高等学校家庭科(家庭基礎・家庭総合)における授業実践
| Ⅰ | 高等学校家庭科の教科科目について
|
|||||
| Ⅱ | 高等学校家庭科における「金融教育」(学習指導要領:平成21年3月告示との関連) | |||||
| 【家庭基礎】 1 内容 |
||||||
| (2) | 生活の自立及び消費と環境 自立した生活を営むために必要な衣食住、消費生活や生活における経済の計画に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、環境に配慮したライフスタイルについて考えさせるとともに、主体的に生活を設計することができるようにする。 |
|||||
| エ | 消費生活と生涯を見通した経済の計画 消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ、適切な意志決定に基づいて行動できるようにするとともに、生涯を見通した生活における経済の管理や計画について考えることができるようにする。 |
|||||
| 【家庭総合】 2 内容 |
||||||
| (3) | 生活における経済の計画と消費 生活における経済の計画、消費者問題や消費者の権利と責任などについて理解させ、現代の消費生活の課題について認識させるとともに、消費者としての適切な意志決定に基づいて、責任をもって行動できるようにする。 |
|||||
| ア | 生活における経済の計画 生活と社会のかかわりについて理解させ、生涯を見通した生活における経済の管理や計画に重要性について認識させる。 |
|||||
| イ | 消費行動と意思決定 消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させ、消費者として主体的に判断できるようにする。 |
|||||
| ウ | 消費者の権利と責任 消費生活の現状と課題、消費者問題や消費者の自立と支援などについて理解させ、消費者としての権利と責任を自覚して行動できるようにする。 |
|||||
| ※ | (3)アについては、家庭の経済生活の諸課題について具体的に扱うようにすること。ウについては、契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題などを取り上げて具体的に扱うこと。 | |||||
図1 新家庭基礎ともに生きるくらしをつくる(教育図書)より一部抜粋
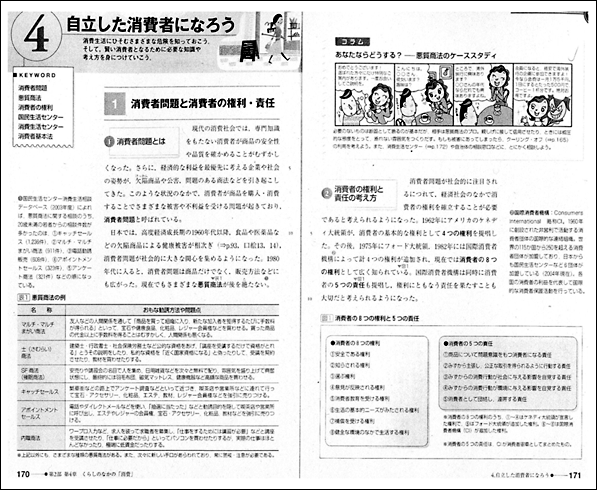
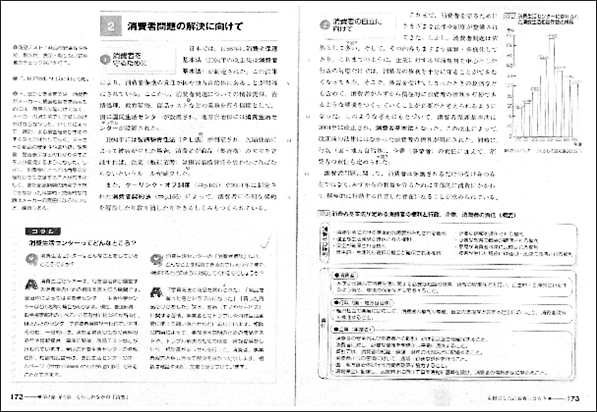
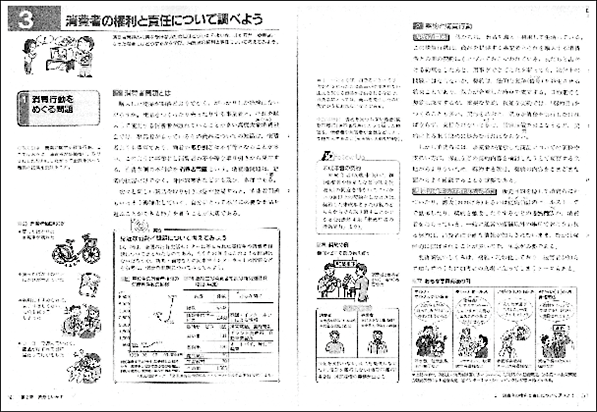
図4 家庭総合生活の創造をめざして(大修館書店)より一部抜粋
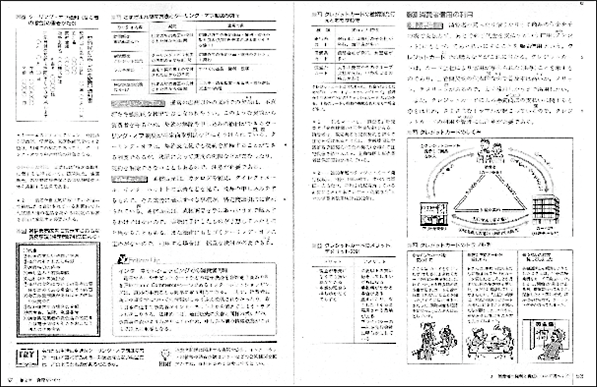
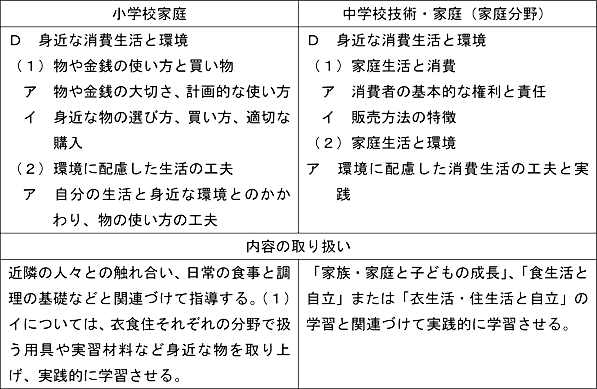
| 1 | 目的 | ||
| (1) | 家庭の経済生活について実際の生活場面を想定しながら総合的に学ぶ。 | ||
| (2) | 消費者の一員として一人暮らしの計画を立てることにより、社会の変化と消費生活及び消費者の権利と責任について学ぶ。 | ||
| 2 | 実施内容【後期課程:4回生(家庭基礎2単位)】 | ||
| (1) | 配当時数 8時間 |
||
| (2) | 実施の流れ詳細 | ||
| [1] | 家庭の経済生活を知る[1時間] | ||
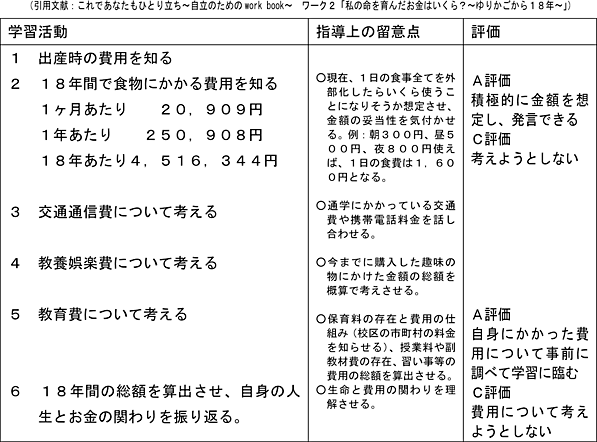 |
| ◎ | 1時間目終了後の成果 ~感想(無作為抽出)~ | |
| ● | すごい。私一人でお金を遣っていたのだなと思いました。親に迷惑かけないように無駄遣いしないように気をつけたいと思いました。 | |
| ● | びっくりしました。まさかこんなにお金がかかっているなんて思ってもいなかったし、考えたこともありませんでした。寮を3年間通って165万円もかかるなんて…。でも私立よりは安いので私立に通っていたらもっとお金がかかったんだなぁ…と唖然です。この学校生活悔いが残らないように頑張ろうと思います。 | |
| ● | お父さんよく生きているなと思った!本当にごめんなさい。 | |
[2] 家計のやりくりを体験するⅠ~構成を指定した家族の家計シミュレーションゲーム~[1時間]
(引用文献:金融教育プログラム-社会の中で生きる力を育む授業とは-※東京都目黒区立目黒中央中学校教諭三枝利多氏)
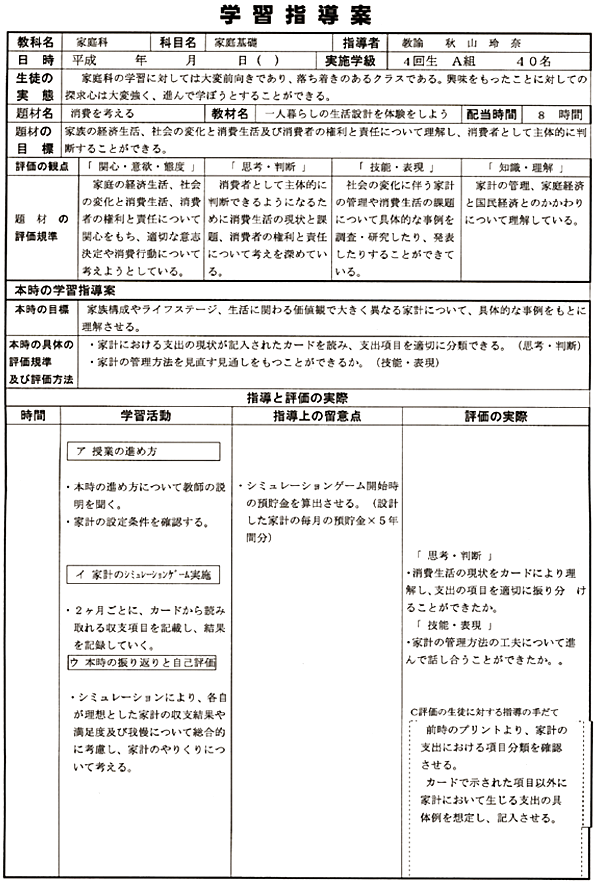
[3] 家計のやりくりを体験するⅡ~一人暮らしの計画を立てる~[3時間]
(引用文献:これであなたもひとり立ち~自立のためのwork book~ワーク7「ひとり暮らしの快適空間」)
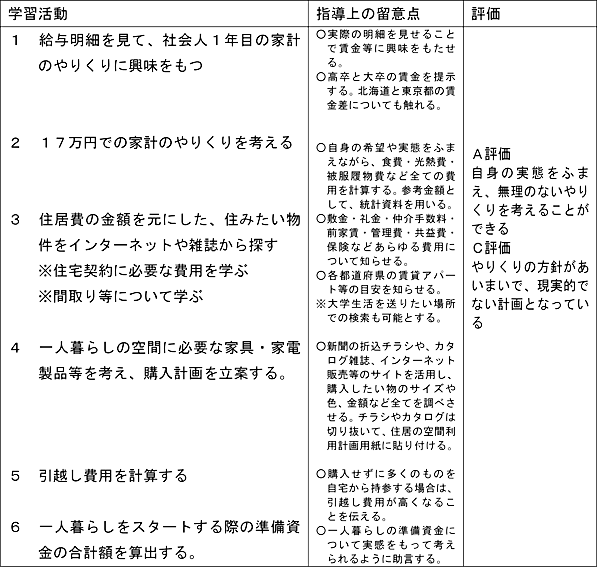
| (1) | [4] | 消費者の権利と責任Ⅰ[2時間] | |
| ※ | 販売方法、契約、クーリングオフについて/クレジットカードと自己破産について知らせる。クレジットカードについては、メリットとデメリットの双方を考えさせる。 | ||
| [5] | 消費者の権利と責任Ⅱ[1時間] | ||
| ※ | 悪徳商法について取り上げ、実例を想定した例文を考えさせる。 | ||
| 3 | 引用資料・参考資料 | ||
| [1] | 阿部智子他:これであなたもひとり立ち~自立のためのwork book~,金融広報中央委員会,2003 |
||
| [2] | 金融広報中央委員会:金融教育プログラム-社会の中で生きる力を育む授業とは-,図書印刷株式会社,2007 | ||
| [3] | 文部科学省:高等学校学習指導要領解説家庭編,開隆堂出版,2005 | ||
| [4] | 牧野カツコ編著:家庭科ワークブック,国土社,1996 | ||
| [5] | 金融広報中央委員会:金融に関する消費者教育の推進に当たっての指針(2002),太平社,2006 | ||
| [6] | 河野公子他:最新ビジュアルワイド家庭科資料+食品成分表,東京書籍,2006 | ||
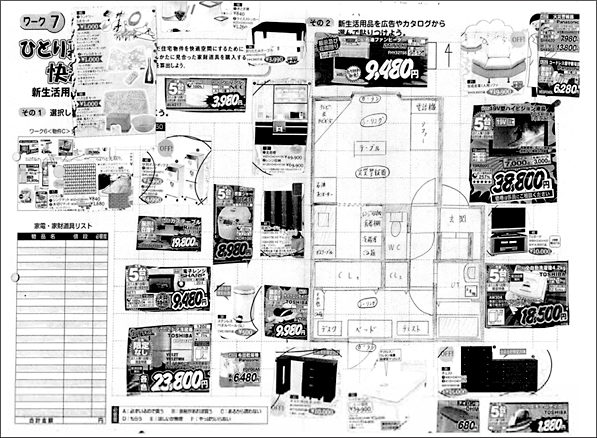
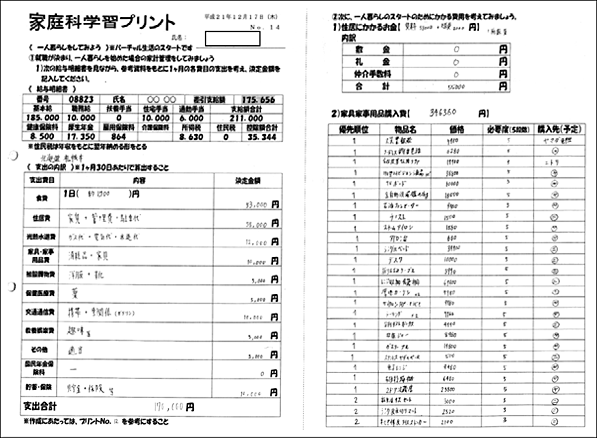
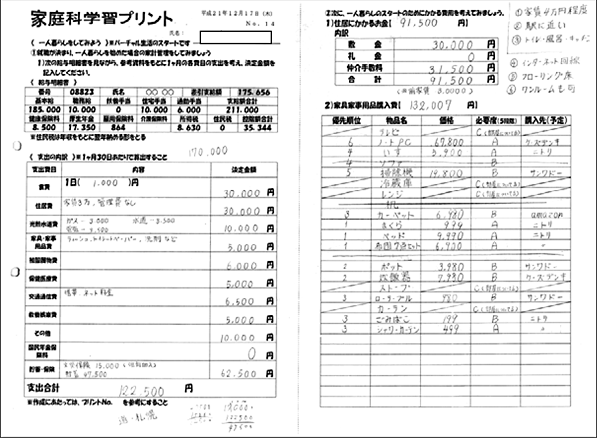
●販売方法について(1時間)
店舗販売と無店舗販売、支払い方法等について学ぶ。関連して、銀行における役割や金利についても学習する。
※ICマネーや、お財布携帯など新しい支払い方法についても取り上げる。
●将来を見据えた家計管理(2時間)
金融商品、金融改革、経済計画と意思決定について触れ、生活設計の違いを考慮した家計管理を行うシミュレーションを実施する。また、ある個人の携帯電話の使用状況を紹介し、その中で最も得をできる契約方法を調査するなど、実生活に応じた学習を行う。
●消費者の権利と責任
身近な消費者問題の例を挙げ、解決方法や対策について学ぶ。体験例を披露し合ったり、解決方法について考えたりする。消費生活センターの存在や所在地についても知らせる。